沌珍館企画 文芸部論文課 「人をあらわすことば」について
|
|
1.人称詞の構造分析日本語の「人を表すことば」の研究という分野では、慶大教授鈴木孝夫氏の研究がかなりの評価を得ている。ここでは『ことばと文化』(岩波新書)を中心に、親族間の「人をあらわすことば」をみてみよう。 まず、家系図に分割線を入れたような形の図1が登場する。なお、「目上」ということは「分割線よりも上」、「目下」は「分割線よりも下」というふうに定義されており、ここから帰納的に五つの原則が導かれる。 (1)目上の親族に人称代名詞を使って呼びかけたり、直接言及することは出来ないが、目下の親族に対してはそれが出来る。 (親に向かって「あなた」「おまえ」は使えないが、自分の子、弟、妹等になら使える) (2)目上のものをふつうは親族名称で呼ぶが、目下のものに対してはそれが出来ない。 (母親を「おかあさん」とは呼べるが、弟を「おい弟」とは呼べない) (3)目上のものを名前だけで呼ぶことは出来ないが、目下のものに対してはそれが出来る。 (自分の兄を「太郎」と呼ぶことは出来ないが、兄は弟を「次郎」と呼ぶことが出来る) (4)目上の人に対して(特に女子は)自分を名前で呼ぶことは可能だが、目下のものに対してはふつうこうは言わない。 (「良子はこれきらい」は娘→母であって逆のケースはない) (5)目下のものに対しては、自分を相手の立場からみた親族名称で言うことが出来るが、目上に対してはそれが出来ない。 (兄は弟に対し自分を「にいさん」とは言うが、弟は自分を「弟ちゃん」とは言わない) なお、原則(3)の「名前だけ」というのは「さん」もふくめて考えたい。つまり自分の兄は「太郎」とも「太郎さん」とも呼べないのであり、「名前だけ」ではない場合というのは「太郎にいさん」という形のことと解する。 鈴木氏はさらにこの(2)と(5)をまとめて「親族名称」だけの原則を提示している。 (A)分割線よりも上(目上のもの)に対しては、相手を呼ぶには親族名称しか使えないが、自分を指すときには親族名称は使えない。 (B)分割線よりも下(目下のもの)に対しては、相手を呼ぶには親族名称は使えないが、自分を指すときには親族名称も使える。 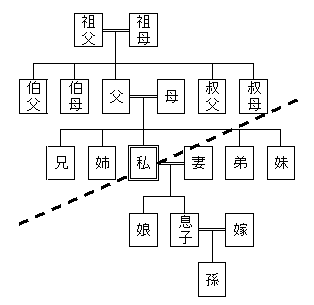
【図1】
2.親族名称と親族呼称さて、親族用語には大きくわけて「親族名称」と「親族呼称」のふたつがある。前者は「父」とか「祖母」とか言う、家庭内での位置や役割を示すものであり、後者は「おとうさん」「おばあちゃん」のように実際に声を出してその人を呼ぶ場合や、「おばあちゃんなんてキライ」のように代名詞的に使われるものである。 しかし、以上の構造分析に関しては、この親族名称と親族呼称との区別がまったくなされていない。昭和42年の『言語研究』第51号のなかの「トルコ語の親族用語に関する二、三の覚え書」(*)においてこのふたつを「言及の用語」と「呼びかけの用語」としてはっきり区別し、かつ区別することを主張した鈴木氏が、すでに翌43年の岩波講座『哲学』第11巻<言語>第9章「言語と社会」のなかで「親族用語で呼ぶ」という包括的な言い回しを使い出し、ついに47年の『思想』第572号(1972年2月号、岩波書店)のなかの「日本人の言語意識と行動様式」において「親族名称で呼ぶ」と言うに至っているのである。前出の『ことばと文化』48年、や『ことばと社会』(中公叢書、50年)においても「親族名称で呼ぶ」ことになっている。 なぜだろう。この区別は絶対に必要なのである。たとえば、前述の原則(2)を見てみよう。これはあきらかに「目上のものをふつうは『親族呼称』で呼ぶが、目下のものに対してはそれが出来ない」とすべきなのである。つまり、例にあがっている「おい弟、とは言えない」というのは「あたりまえ」の話なのだ。「弟」というのは「父」と同じく親族名称なのであって、「おい弟」とは言えないというのは、「ねえ父」とは言えないのとまったく同じなのである。 分割線云々以前の問題として、「親族名称では呼びかけることは出来ない」。ここをはっきりさせずに「父概念を含むことば」などと言っているのは極言すればいわゆる「本末転倒」であり、けっきょく原則(2)は「ねえ、おとうさん」と一緒に「ねえ、父」という恐るべき表現を正当に受け入れなければならなくなるであろう。原則(5)についてもまったく同様である。「親族名称で呼ぶ」のであれば、なにゆえに「お父さん」「とうさん」「とうちゃん」「パパ」などに対して「父」だけが排除されるのかの説明がつかない。 以上をまとめてみれば、原則(2)(5)(A)(B)の「親族名称」は「親族呼称」でなければならず、(2)の例としては、弟を「弟さん」とは呼べないことをあげるべきであることが判る。「弟さん」というのは相手や他人の弟に言及するときにしか使えないのである。 (*)この文献をこころよくお貸し下さった鈴木孝夫教授と、その全文コピーをしてくださった慶応義塾大学言語文化研究所の事務員の方に、改めてお礼申し上げます。 3.「妻」は目下の概念かつぎに夫婦間の呼称の問題を考えてみよう。まず最初に驚くのは、「夫と妻」という関係でとらえると、メンと向かって言及できる親族呼称が、相手に関しても自分に関してもまったくないということである。 確かに、「夫」「妻」という名称に対して、呼称としては「旦那(さん)」「亭主」「主人」「(うちの)ひと」や「奥さん」「女房」「家内」「細君」「かみさん」「(うちの)やつ」などなど、かなりある。しかしこれらのことばは、実際の夫婦の間においては、あの「おかあさん、ちょっと」という呼格的用法も、「おかあさんなんてキライ」という代名詞的用法もおよそあてはまらないのである。「旦那(さん)」「奥さん」という呼びかけは他人の「旦那(さん)」「奥さん」に対して使われるだけである。これらのことばが自分の「本物」を指すことがあるとすれば、それは第三者との会話の中での言及である。そしてこの場合でさえも、「うちの〜」という形のほうが使われやすい。したがって以上のようなことから、夫婦間においては自分にせよ相手にせよ、およそこれらのことばで「実際に呼ぶ」ということはありえないのである。 さて鈴木氏は昭和43年の「言語と社会」(前出)という論文のなかで、自分を夫とすると妻は自分よりも「目下」の概念になることを述べている。48年の『ことばと文化』では「いちおう同位者と考えておく」とされていたが、50年の『ことばと社会』では最初の「言語と社会」のものがそっくり再録されている。なお決定的なことには、47年の『思想』の論文以来ずっと出てくる図1では明らかに妻は分割線よりも下に位置している。では、その「妻は目下」の理由を見てみよう。 まず、一家庭内では目上は年上と同義語だとされるが、夫と妻ではその年令差は関係しないことが述べられる。(余談だが、ここに出てくる「ところが夫と妻の年令差は一定していないし、またどちらが必ず年上ということもない」という文は理解に苦しむ。親子兄弟どれをとっても年令差は一定してはいないし、まさか結婚式と金婚式で年令差が変わるわけではあるまい。必ずどちらかが年上ということはない、というのであれば後半の部分とダブる。しかしこんなところをつつくのが研究者の使命ではない) ここで三つの例があげられる。 (ア)名前で呼ぶ時には、「良子」に対し「太郎さん」と夫のほうが優位。 (イ)「あなた」「あんた」は互いに使えるが、妻は夫を「おまえ」「きみ」とは言わない。 (ウ)子供が生まれると互いに「お父さん」「お母さん」と呼ぶようになるが、妻は夫を名前では呼ばなくなるのに対し依然として夫が妻を名前で呼ぶケースもある。 しかし(ア)と(イ)は「川崎、ちょっと」「なんですか、井島さん」の会話から上下を割り出すような、同種のことばのなかの「程度」の差に注目しただけであって、原則(1)から(5)までのような、親族名称・人称代名詞・名前などの種類の異なることばを対比させて出てきた結論ではない。(ウ)にしても夫も妻を名前では呼ばなくなることを排除しているわけではない。このようないわば見当違いの例であるにも関わらず、これらを「前に述べた家庭内の呼称の全体的な体系にあてはめて解釈」し、これから「夫は妻を呼称の体系上は子供と同列に置くことがあるが、妻のほうは子供の立場に同調して夫を見ることが多くなる」として、「多くの場合、子供が生まれると妻は目下、夫が目上の地位を占めるようになる」と結論する。 ならばそのように「夫は目上、妻は目下」としてしまうとどういうことになるかを見てみたい。 まず原則(1):目下であるはずの妻が目上であるはずの夫に対して「あなた」と呼びかけ、「この本あなたの?」と言える点において「成立しない」。 原則(2):目上であるはずの夫に対し、妻は夫に関するいかなる親族呼称を用いても呼びかけることはできない点において、これも「成立しない」。 原則(3):目上であるはずの夫に対し、妻からも「太郎さん」と呼びかけることが出来る点において、これもやはり「成立しない」。 原則(4):これは成立しうる。しかし妻が「良子これキライ」と言いそうにないのは彼女の年令的要因からであって夫との関係からではない。 原則(5):目下であるはずの妻に対して、夫は自分自身を「夫」に関するいかなる親族呼称を用いても指すことはできない、という点において「成立しない」。 この結果はどうだろう。なんと五つのうち四つまでが成立しないのだ。背理法的に考えれば、「夫は目上、妻は目下」という前提がおかしいことになる。とことが逆に「夫は目下、妻が目上」としてみても、結果はまったく同様なのだ。 鈴木氏はこの考察に入る前にこう述べている。「…以上のような理由で、少なくとも現代の東京では言葉の分析に先立って夫と妻のどちらが高い地位かを決めておくことは出来ない。むしろ夫と妻の間の、実際に使用される呼称、自称を調べて、それを家族内の呼称の全体的なパターンに整合するよう位置付けることによって、相互の地位を夫や妻がどう感じているかを知ることが出来るのである。つまり、言語的な指標から逆に夫と妻の地位の相対的関係を見ようというのである。」 この方法論自体に問題はない。しかし、原則(1)〜(5)を使って作り上げた「家庭内の呼称の全体的なパターン」に「整合するよう位置付け」られたはずの「夫は目上、妻は目下」という結論が、完全試合は逃したものの、五つのうち一つだけを残してあとの各個撃破に凱歌をあげているというのはどう考えても納得がいかない。 もうひとつ。妻を目下としたのなら、その呼称である「おくさん」はもちろん目下の呼称である。そしてこれらは明らかに他人に対して使える、というより、他人に対してしか使えない親族呼称である。なのになぜ『ことばと文化』には以下のような記述があるのであろう。「…したがって(血縁関係のない他人に対しても)目下の地位を表す息子・倅・孫そして甥・姪などのことばは使えないのである。しかし娘だけは「娘さん」という呼びかけが可能である…」 4.原則(6)の設定「以上」の「異常」な事態は何を意味するか。はっきり言って夫婦間の呼称問題を目上だ目下だとやっている限り例の諸原則は玉砕するのである。妻は「ここでは一応」などというのではなく、本当に「同位者」なのだ。分割線より上でも下でもなく、いわば「分割線上に夫と並んで」いるのである。したがって、書くとすれば図2のようになるはずである。 (1)から(5)までの原則がすべて目上と目下に関するものであるから、目上でも目下でもない、したがって(1)から(5)までの領域に入らない「同位者」に関する原則は新しく作り出さなくてはならない。そこで、同じく帰納的な方法によって原則(6)を設定する。 (6)分割線上に自己と並ぶ同位者に関しては、その関係を正しくあらわす親族呼称は自称、対称ともにいっさい使えない。 したがって夫婦は正規の親族呼称以外の呼び方、つまり名前や人称代名詞で呼ぶことにならざるを得ない。さらにはその名前や人称代名詞、つまり「太郎さん」「良子」や「あなた」「おまえ」「きみ」などということばがきわめて直接的で明示的であるがために、そのことがある意味でその直接性、明示性を避けて「おとうさん」「おかあさん」式の呼び方に移っていく心理的な素地を作っているのではないかとさえ思える。 そして何よりも、「おとうさん」「おかあさん」には「良子」「太郎さん」や「あなた」「おまえ」に感じられる、妻を一段下げたニュアンスがないことに注意すべきではないだろうか。前出の「トルコ語の親族用語に関する二、三の覚え書」から引用してみよう。 「(トルコでは)都会の若い世代の夫婦は名前で呼び合うことも珍しくない。これは日本なども含めて、一般に伝統的社会がいわゆる近代社会に移行する際に見られる夫婦間の社会的地位の落差の解消と結びついている現象である」 トルコ語ではkoca(夫)をefndiと呼び、kari(妻)をhanimと呼ぶ事による地位の落差(日本人には判らないけれど)を、お互いに名前だけで、たぶん「さん」等のもの無しで呼び合うことによって解消したのなら、日本では「おまえ」「あなた」の落差を「太郎」「良子」では納まらずに「太郎さん」を残したが、結局は「おとうさん」「おかあさん」の相互平等性をもってその差を無くしたと見てよいであろう。 また、この原則(6)はなにも夫婦間に留まることはない。自己の意識の問題として、同位者は他にもいる可能性がある。たとえば、自分の「いとこ」の場合は同位者と考えたほうが妥当な場合が多い。「いとこちゃん」という呼びかけは使われず、たとえ年上でも名前を使って呼んだり、あるいは「おにいちゃん」にしてしまったりする。また鈴木氏が「例外」として出した「近年の都会での、年令の近い姉妹が相互に名前で呼び合うケース」もちゃんとこれにあてはまるのである。以前は「姉を同位者(同格者)として見る」などということがなかったからにすぎない。要は意識としての同位者概念であるから、この妹が姉を「おねえちゃん」と呼ぶ時は既に(甘えるか対抗するかで)姉を同位者ではなく目上とみなした場合であり、既に原則(6)の領域を出てしまっているから、原則(6)における否定的表現は影響しない。 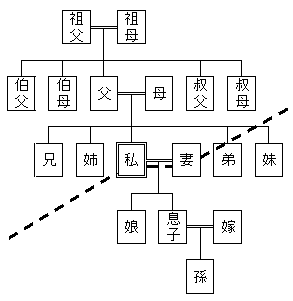
【図2】
5.子供の発想の先取りしかし、所詮以上のような機能的構造分析では「使われ方」あるいは「使い方」は明らかになっても、どうしてそうなるのかという問題に迫ることは出来ない。そこで、これらの人間関係の認識とことばとの関係を見てみようと思う。 鈴木氏は夫婦が互いに「おとうさん」「おかあさん」と呼び合うのを、相手は自分の父や母ではないことから「親族名称(正しくは呼称)の虚構的用法」とし、呼称の原点を子供に置くからであるとした。夫と妻ではなく、父であり母であるという「固定し安定した役割」が呼称を変えさせた、と見ている。 しかし、ここには役割と呼称との関係における見落としがある。つまり、『ことばと文化』から引用すれば、「ただ面白いことに、ある特定の親族集団(家族)に属する目下の、目上に対する呼びかけと、その目上が自称詞として用いる親族用語は一致する。つまり、自分の子供から「パパ」と呼ばれる父親は、子供に対して自分を「パパ」と言って「おとうさん」などとは言わない」―この現象を「ただ面白いことに」として片付けてしまったのがいけないのである。お互いを夫婦としてとらえるよりも、「同一の子供の父であり母であるという与えられた関係」として、つまち「父母の役割」としてとらえるだけならば、子供が「おとうさん」と言うからといって、自分も「おとうさん」にする必然性はまったく無い。「パパ」でも「おやじ」でも「とうちゃん」でも、父の役割の確認という点に関しては「おとうさん」とまったく同じなのである。 思うに、「虚構的用法」というのは「相互関係の追及」の結果ではなく、「認識の共有」の手段なのではないだろうか。この点で三浦つとむ氏の「子供のことばの先取り」という説には賛同できる。子供にとっての「父である」からではなく、子供が自分を「おとうさん」と思うからこそ自分は「おとうさん」のほうがいいのであって、決して「パパ」ではないのだ。同様に子供が「妻」を「おかあさん」と思うからこそ彼女は「おかあさん」のほうがいいのであって決して「ママ」ではなく、ましては「良子」や「おまえ」ではない。したがってこの段階ではこの「おとうさん」「おかあさん」は本質的には幼児語である。 『日本語の文法』(勁草書房)のなかで三浦氏はこの問題にふれ、幼児との会話では「聞き手である幼児が“おとうさん”“おかあさん”という発想を持っているのだから、そのことばを借りて自分も同じ発想で表現したほうが、その表現の“受け手”である幼児としても自分の発想のままでスムーズに追体験(=理解)できるのである」としている。これがつまり子供の発想のことばの先取りなのであって「観念的な同一化を容易にする」方法であり、表現に先立つ役割確認よりも相互の表現内部の「同一コード化」と見たほうがよいように思う。ビートルズを知らない人には「アビイロード持ってきて」とは言わずに「ちょっとそのレコード持ってきて」と言うが如しである。祖母が孫の立場におりてから自分の娘である母親を呼ぶだけなら「おかあさん」だろうが「かあちゃん」だろうが「ママ」だろうがどれでもよいことになる。しかし、この赤ん坊の「ママ」という発想を考えると、同一人物を指すのに「おかあさん」では幼児との共通コード体系の上には立てなくなるから同じことばを使うのであって、ここは「母」の役割確認などというものではない。 もうひとつ例をあげてみよう。テレビの「体操のおにいさん」についてである。彼は(a)子供達からも、(b)自分自身の口からも、(c)司会者がいれば司会者からも、「体操のおにいさん」と呼ばれる。「体操のおにいさん」は固有名詞だとしてしまえばそれで終わりのようだが、ではなぜ「おにいさん」かという問題が残る。そこで(a)は自分と親族関係を想定して「おにいさん」と言った第一の虚構的用法による対称詞、(b)は親族関係を想定した第一の虚構的用法で相手に原点を移してそこからとらえた自称詞、そして(c)司会者が「年下」の彼を「おにいさん」と言うのは、「その下に」弟か妹を想定してそこからとらえる第二の虚構的用法、ということになる。 しかし、(c)は明らかに違う。司会者が彼をとらえる視点は彼の虚構的な弟や妹、つまり「彼の家族の最年少者」からではなく、そこにいる子供達からのはずだ。したがって、彼の虚構の弟や妹への視点移動のあとにそこから「兄」として見ているのではなく、子供へ視点を移したあとさらに虚構の親族関係を投影していると見なければならない。するとこれは第二の用法ではなくて第一の用法である。(詳しくは『ことばと文化』を参照されたい)しかし、「おにいさん」と呼ぶ相手は自分より「年下」なのだ。これは鈴木流には説明できない。 同じようなケース、つまりNHKの「子供ニュース」での「川でおぼれたおともだち」は、アナウンサーのお友達ではなく、ニュースを聞いている子供達に同調してとらえた「彼らの」虚構的なおともだちなのだ、ということを、「拡大された奇異な用法」として片付けてしまったために、「助けてくれた高校生のおにいさんは」という「アナウンサーの」発言にまで分析が届かないのである。もちろん、だれもこの英雄に弟を想定したりはしない。つまり「なぜ」このアナウンサーやニュースライターは彼の弟にではなく、「ニュースを聞いている」子供達に同調したのか、という点である。 だがこれに先ほどの考え方を当てはめてみれば事態は簡単に説明がつく。(a)はもちろん、ことばの発し手である子供達が彼に対して「おにいさん」という発想を持っている事そのままであり(これについては後に述べる)、(b)(c)そして「高校生のおにいさん」は、その対象に関しての、「その表現の受け手」である子供達の発想、そのことばの先取りなのである。追体験が容易になるように、「聞き手・受け手」である子供のことばそのものを使ったにすぎず、それぞれの間で彼を指すことばに関して共通のコードの上に立ったものと見ることができる。 6.夫婦間の相互呼称以上のようなわけで、子供が「おかあさん」と発想するから、そのことばを先取りして母親は自分を「おかあさん」と言うのだ、ということになったが、子供はあらかじめ「おかあさん」という発想を持って生まれてくるわけではない。「役割認識」のようなものがあるとすれば、この段階でのはずである。自分を「ママ」ではなく「おかあさん」だと思わせたいなら、「おかあさんだよ」と名のりをあげていけばよい。自分を「おかあさん」と呼ぶことは、鈴木氏による「自分で<私が母親>という役割を確認」し、間接的に相手である息子に「<自分は息子>という役割の確認」をせまるというようなそれぞれの自分の役割確認のためではなく、むしろまったく反対に、息子の側に「相手は自分の<おかあさん>ということの確認」をせまっていることになる。この点は三浦氏も指摘している。自分の娘を「ママ」と呼ぶ母親は、孫である赤ちゃんに彼女を「ママ」と呼ばせたいからこそ、(ほとんど無意識に、つまり「おかあさん」ではなく)彼女を「ママ」と呼び始めるのであって、このひとが「ママ」だよということを、つまり役割よりはほとんど「なまえ」を、共通コードの上で「赤ちゃんに」押し付けているのだ。「ママ」の方ではそんな事は判りきった話なのである。 入谷敏男氏は『ことばの心理学』(中公新書)のなかの「ことばの発達心理」という章においてこのへんの現実を取り違えているのではないかと思われる。以下引用してみる。 「…たとえば(幼児は)「パパ」という語を自分の父親ばかりか親戚の男の人にも見知らぬよその人にも使う。(しかし)時を経るにしたがって自分の父親とその他の成人との違いが判るようになり、「この人は自分の父親ではない」という意識が漠然と生じ、その後しばらくして「オジチャン」という語を覚えるようになる」 とんでもない話である。子供が父親や母親を認識する能力は、動物行動学で言う「インプリント」、ほとんど「焼き付け」に近い。いま抱いてあやしてくれいるのは父親かちがう人かの区別はほとんど本能的に直感する。これはただ「パパ」ということばの使い方がまだよく判らないためなのだ。 したがってこの子が親戚の男の人をも「パパ」と呼んだときには、パパということばの「使い方をよく知っている」まわりのおとなたちが「ちがうよ、パパはこっち。この人はオジチャン」と、「ことばの使い方」を強引に教えていくのである。決して「時を経るにしたがって違いがわかるようになり」「その後しばらくしてオジチャンという語を覚える」などというものではない。「オジチャン」までも「パパ」と呼んだ時に「そうじゃない」とチェックされてそれぞれの定義が教え込まれていくのだ。この過程については外山滋比古氏が『ホモ・メンティエンス』(みすず書房)のなかで、服部四郎氏が「意味」(岩波講座『哲学』第11巻第8章)のなかで、それぞれイヌとブタ、イヌとネコの例を用いて明快に説明している。 以上、「ママ」「おかあさん」などのことばはほとんど「名前」として赤ちゃんに押し付けられることになる。しかし、これらのことばを覚える頃の子供には「母=子」という対概念などまだほとんど理解できない。かくして「ママ」や「おかあさん」というのは「このひと」のいわば固有名詞のようなものになるのである。これは次の前人称性とも関連する。 ここで愛読書のひとつである石井桃子著『ノンちゃん雲に乗る』(角川文庫)から引用してみよう。「…おかあさんの名前…(中略)いま考えてみればずいぶんおかしな話ですが、学校へあがるずっとまえのノンちゃんは、それに気が付かなかったのです。(中略)おかあさんは、ノンちゃんのおかあさんで、世界中どこへ行っても「うちのおかあさん」「あたしのおかあさん」ですむものと思っていました。けれど、おかあさんは…ほんとは「田代雪子」さん、という人だったのです。なんという不思議なことでしょう。…それはノンちゃんにとっては大きな発見でした。…」 ノンちゃんのように、「何とも言えない、不思議な気持ちに打たれ」て、「おかあさん」は「名前」ではないことが判るようになるまでは、子供のほうでは固有名詞モドキが相手では自己の役割規定もなにもないのである。 こうして、今度は父親のほうで、子供が固有名詞的な「おかあさん」という発想とことばとを持っているのだから、その同一人物である妻を「おまえ」とか「良子」と呼ぶことによる混乱を避け、理解しやすい子供の発想そのままの「おかあさん」で妻を呼ぶことになるのである。これは幼児に、食べる行為とその対象を「食事」とは言わずに「マンマ」と言うのと根本的には何ら変わりはない。 かくして両親は子供の発想を引き取ってそれぞれを「おとうさん・おかあさん」「パパ・ママ」と呼ぶようになる。しかしこの段階ではまだその場で「幼児語」を引き取ったにすぎない。三浦氏も言っているように、確かに、「父親が母親を呼び捨てにするのを子供が聞いてどう感じるのか。子供がその呼び方をまねた場合はどうなか」を考えれば「おとうさん」「おかあさん」という呼び方は「子供に対するしつけとしても役に立つ」ことにもなるであろう。たとえば、ぼんやりと固有名詞的に受け取られていたことばが変わった使い方をされると、子供は意外にするどく反応する。 「うちのおとうさんは、おじいちゃんのこと、とうさん、とうさん、って言うのでとってもオカシイです」(51年9月15日敬老の日にラジオで聞いた小学6年生の声)「おじいちゃん」を「とうさん」だから「とってもオカシイ」ぐらいですむのかも知れないので、「おかあさん」を「良子」「おまえ」だったらもう少し反応は違うかも知れない。 しかしこんなものは「副産物」だとして、やはり三浦氏も、前に述べた「おとうさん」「おかあさん」が相互に格差のないことばであることを重視している。これが、子供をある程度意識しないでも「おとうさん」「おかあさん」が夫婦の相互呼称としてそれだけで成り立つ要因と言えるのかも知れない。この点に関しては第4節で既にふれたので、『日本語の文法』から引用するに留めたい。 「…おとうさん、おかあさんは子供が毎日使っていて誰が聞いてもおかしくないことばである。たとえ夫が妻を「おかあさん」と呼んで「さん」付けになっていても、第三者が聞いて(「良子さん」の場合のように)甘い男だと思いはしない。そこでこれらの子供の呼び方を相互呼称に借用することで形式的に相互平等の立場に立ち、子供からの尊敬をもとにした、しかも「夫婦としての」愛情や尊敬を込めた表現が気兼ねや抵抗なしに使えるようになり、両親とくに第三者の手前、差別的表現を強いられてきた母親に歓迎されるのである。」 7.前人称的言語最後に、先ほどの「助けてくれた高校生のおにいさん」の分析から先に進んで、公園で泣いている小さな女の子に「おねえちゃんの名前なあに?」と聞く場合の虚構性を考えてみよう。 鈴木氏はこれを、その家族の最年少者の観点に同一化するからだと説明した。つまりその女の子に弟か妹を想定し、そこから「おねえちゃん」ととらえるのだという。しかし残念ながらこれも前と同様、役割と呼称とを一元的に考えた結果にすぎないように思われる。つまり、弟か妹を想定し、そこから「姉」としてとらえるならば、たとえば「おねえさん」でも「ねえちゃん」でもよいはずである。しかし、このような状況で「ねえちゃんの名前なあに?」という表現がはたして考えられるだろうか。また、「おねえさんの名前なあに?」と聞いてしまえば、実際に姉がいればそっちの名前を答えるであろうし、いなければ「あたしにおねえさんいないのー」と言ってまた泣くのではないか。 この件に関しては岩波講座『文学』第3巻<言語>第1章第2節、田島節夫氏の「言葉と社会」が参考になった。まず、人称代名詞は「転換詞」であるとされ、ロマーン・ヤコブソンが『一般言語学』(みすず書房)の中でこの転換詞の不思議な機能の習得は子供にはなかなか容易ではないと指摘していることが重くみられる。つまり転換詞は普通名詞と違って、一度にひとつの対象しか指すことが出来ないにもかかわらず、また固有名詞とも違ってそのつど違ったものを指すことが出来るのである。この難しさは田島氏が引いた次の例でも判る。「きみはきみのことをぼくと言ってはいけない。ぼくだけがぼくなんだ」 そしてさらに難しいものとして親族用語があげられる。「親族名称は、子に対する父、弟に対する兄、というように関係を含む言葉であり、対称詞として話し手自身との関係で使われる場合は、話し手が変わるにつれて別な名称で呼ばれなければならない。だから、同じ人間の名称が転換詞の場合よもはるかに複雑に変動するわけであり、このような事情が子供にわかるようになるのはよほど後のことであろう」という訳である。例をあげれば、オジイチャンがトウサンでもありニイサンでもありオジサンでもあるような事である。 しかし、田島氏いわく「ひとりの人間にとっては同じ親族名称(呼称!)で呼ばれる人物は一定しているから、固有名詞や普通名詞の場合と事情は変わらないことに注意せねばならない。このことは、子供がまず自分を中心にしたまわりの人たちの親族名称(や呼称)を教えられた場合、固有名詞や普通名詞と使用上の区別がまだないことを意味するであろう。だとすれば、あかの他人が「おじさん」「おばさん」「おじいさん」「おばあさん」と呼ばれることは、少なくとも子供自身にとっては『親族名称の虚構的用法』というようなものではない。それはむしろ、新たに見い出された個体に既知の普通名詞が適用される場合と異なっていないはずである。」 このような、人称代名詞と固有名詞、親族呼称と普通名詞との使用上の区別がまだはっきりしていないような子供の言語を、田島氏は「前人称的言語」と呼んだ。注目すべきは、この「前人称性」のために、結局は子供が他の親族名称を覚え始める時期、まさにこの時期に、子供にとって一般的に考えられる「祖父」が、「おじ」が、「兄」が、それぞれ何才くらいであるかが、かなり幅はあるにせよ、「おじいちゃん」「おじちゃん」「おにいちゃん」ということばの年令を指定してしまうのではないか、ということである。 「父の父を…云々」という親族「関係」ではなく、このくらいの年の人は「おじいちゃん」、という把握の仕方なのではないだろうか。「関係」ではなく「年令」だとすれば、父の父の兄でも、見知らぬ人でも「おじいちゃん」であることに変わりはない。区別を付けるとすれば、親戚のおじいちゃんはそこの地名を付けて「名古屋のおじいちゃん」にするし、玄関に来た見知らぬおじいちゃんは何と言っていいか判らず「へんなおじいちゃんがきたよ」にまでなりうる。 年令で考えるとすれば、「おねえさん」と呼ばれるべき「知らない女の人」が、「おばさん」と呼ばれると不愉快になるのも説明がつく。虚構の親族関係を取り違えられたためではない。実際の親族関係でも、親が多兄弟の上のほうである場合には、その末っ子などは自分とかなり年令が近いことがありうる。しかし、相手が大学生くらいであればいくら「おじ」でも「おじさん」とは呼ばない。また「おじいちゃん」はいやだからと言って「おじちゃん」になっている祖父も少なくない。これらの例からも、相対的関係よりは絶対的年令に重きが置かれていることが判るであろう。そしてこれらは、子供がこれらのことばを覚え始める時期にほとんど確立するのであるから、「目上・目下」の呼称が「呼称としての機能」をほとんど持っていないのも半ば当然である。 そして前に戻れば、「おねえさん」と「おねえちゃん」ではその指定年令層が違うのである。「おねえちゃん」はもっぱら小さな女の子に対して使われる。そのくらいの女の子は、「おねえさんの名前は?」などと聞かれると、外山滋比古氏力説の「冗語成分の風化」を補って(そんなムズカシイことは考えないだろうが)「あなたのおねえさんの名前は?」と理解してしまうのだ。つまり、自分は「おねえさん」という呼称にみあう年令ではないことが判るのである。 日本語の「相手を指すことば」が職業・地位・親族などに関することばや、多くの二人称代名詞などによってほとんど無数に分化しているということは、英語ならば誰彼かまわずyouとして済ましてしまうところを、相対的関係や相手自身の特殊性を取り上げることによって、相手が自分を呼んでいるのだとすぐ確認できるという長所につながる。いまの「おねえちゃん」と「おねえさん」の例がそれをよく示すであろう。 この問題に関して、「おじさん」と「だんな(さん)」の違い、「おばさん」と「おくさん」の違いも重要である。これは必ずしも年令的要因ばかりではないからである。しかしこれも親族云々の見地からもっと広く「人をあらわすことば」として見てみれば、紺の制服で交番にいる人を呼ぶのに「おじさん」とは言わずに「お巡りさん」と言うのと同様、年令に服装、職業やその場の状況までをも含めたことばの選択の過程において、広範囲にその対象に相応しいことばを選んだものと見ることができよう。 以上、目上の親族呼称というのは、前人称的に、年令を(もちろん性別も)指定した一種の普通名詞とみてもよいと思うことを述べた。ただし、「パパ・ママ」や「おとうさん・おかあさん」はそう滅多やたらに本人以外の人に対して使われては困ることから、前に述べたようにすぐチェックされてしまうというだけなのである。目下の親族呼称についても、前人称的世界では「指すものがない」ことからその機能は発達しないことも述べた。最後に鈴木氏が『ことばと文化』で提出した、目下の呼称である「娘さん」について少し述べてみたい。 鈴木氏は「娘さん」だけは、としているが、それらしきものは「お嬢さん」「お嬢ちゃん」「坊や」「坊ちゃん」など、他に無いわけではない。しかし、「娘さん」も含めて、これらは子供が「前人称的」に、親族呼称と普通名詞・固有名詞などの区別があいまいであるために発達(子供の側のみでなく、大人の側でもそのことばを先取りするために相乗効果を生んで発達)した呼称ではない。スナックかなんかの女主人を「ママ」と呼び出したのと同様、「大人」のほうでいわば必要にせまられて使いだした普通名詞である。そのなかで「娘さん」というのはことばの形の上での親族呼称からの採用にすぎない。使用法上の類推から、このように発生的にまったく次元の異なるものにまでも同じ考え方をあてはめようとするのは、やはり無理があろう。 ともかく、「娘」は目下なのに、などと考えるよりもまず、どうして街の良からぬ連中が若い女性に「おう、ねえちゃん」と言ってカラむのか、ということをもう一度考え直すべきではないだろうか。これはどう考えても、その下に弟か妹を想定してからの表現ではないであろう。 参考文献
増渕光伸「人をあらわすことば」について、昭和51年(1976年) 一橋大学津田塾大学日本語研究会『日本語の中へ』第1号収録のまま |

